『イトウを守る、川と魚を取り巻く未来』平田剛士/フリーランス記者、オビラメの会
2010/06/27、2017/09/11
アースデイEZO2010「ボーダレス和太鼓とたくさんのひとつ」レクチャー&交流会
2010年6月27日午前10時、札幌市立札幌大通高校
 本日は、ようこそおいでくださいました。私はフリーライターで、市民グループ「尻別川の未来を考えるオビラメの会」の広報担当幹事を務めている平田剛士と申します。このようにお話しするチャンスを与えてくださった杉山譲司先生や、このEarth dayイベント「ボーダレス和太鼓とたくさんのひとつ」を主催されたみなさんに、深く感謝申し上げます。
本日は、ようこそおいでくださいました。私はフリーライターで、市民グループ「尻別川の未来を考えるオビラメの会」の広報担当幹事を務めている平田剛士と申します。このようにお話しするチャンスを与えてくださった杉山譲司先生や、このEarth dayイベント「ボーダレス和太鼓とたくさんのひとつ」を主催されたみなさんに、深く感謝申し上げます。
さて、北海道にイトウという珍しい魚がすんでいる、ということは、最近ではずいぶん多くの人が知ってくださっています。でも、イトウってどんな魚なのかとなると、まだまだ理解は浅いかもしれません。なにしろ「幻の魚」と呼ばれる生物です。あえて英語で言ったら「ファントム・フィッシュ」、もう一度日本語に翻訳したら「幽霊魚」ですからね、実物を見たことがある人はごく少ないわけです。私たちのグループ名は「オビラメの会」というんですけど、この名前を見て、「へえ、イトウってヒラメの仲間だったんですね」と納得顔で言われたことがあります。オビラメというのは、アイヌ語の名前に由来しているんですけど、それが勘違いされちゃったんです。
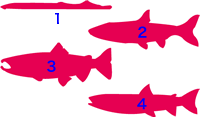 では、みなさんはいかがでしょう。というわけで、シルエットクイズ! 4枚のシルエットのうち、さて、どれがイトウでしょうか?
では、みなさんはいかがでしょう。というわけで、シルエットクイズ! 4枚のシルエットのうち、さて、どれがイトウでしょうか?
現在の北海道には、外来種を含めて、だいたい70種ぐらいの淡水魚が生息していると言われています。これみんな北海道の淡水魚なんですけど、シルエットだけでも、いろんな特徴に気づかれると思います。
1番は、カワヤツメです。厳密に言うと魚類ではなく、円口類あるいは無顎類と呼ばれる生物群の一種です。
2番から4番は魚類ですが、体の形が違うし、ひれの数や位置も違っています。2番はウグイです。ウグイの背中には背ビレが1枚なのに対し、3番と4番は、背ビレの後ろにもう1枚、小さいのがついてますね。「あぶらビレ」といって、これはサケ科の魚の特徴のひとつです。
1番も2番も違うとなると、つまりイトウはサケ科の仲間だということです。3番はその名もズバリ「サケ」、秋になると豊平川にも遡上してくる、あのサケです。サケ科の魚には、性成熟すると体色や体形が急激に変化するものがあって、このサケのシルエットは、北太平洋から故郷の川に戻って、これから繁殖行動を始めようとする時のものです。口先が鈎状に曲がって、サケの鼻曲がりと呼ばれます。
そして4番がイトウです。サケと比べて、ずいぶんずんぐりしたスタイルです。じつはサイズもずいぶん違っていて、正しい縮尺で並べ直すと、こんな感じになります。
で、これがイトウの実物です。大きいでしょう? 体長1mと少しあります。釣り師さんにすればもちろん超大物ですが、北海道での最大記録は体長2.1mという個体で、この魚の倍のサイズということになります。
イトウ研究の第一人者で、北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場の川村洋司さんに、イトウの魅力って何でしょう、とインタビューしたら、「目の前の川の中に、こんな大きな魚が悠々と泳いでるだなんて、その姿を想像しただけでもワクワクするじゃないですか」と答えてくれました。みなさんもぜひ、川を見ながら、もしここにこんなイトウが潜んでいたらって、想像してみてください。
かつて東北地方の川でも捕獲記録が残るイトウですが、ここ1世紀間に分布域は急速に狭まってしまいました。その原因は必ずしも突き止められていませんが、やはり人為的な環境破壊の影響が大きかったのではないでしょうか。10年ほど前に発行された北海道レッドデータブック(RDB)では、イトウは最も危険水準にあるという意味の「絶滅危機種」にランキングされました。2006年に公表された国際自然保護連合のレッドデータでもCR(ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種)という最悪ランクで、国内的にも国際的にも「絶滅の危機に瀕している」と判定されているわけです。
ところで、そんな風に判定されてRDBに載ったら、イトウにとってどんなメリットがあるとお思いですか? じつはほとんどありません。イトウに限りませんが、RDBに掲載されたからと言って、実際に保護の手が差し伸べられるかというと、全く期待はずれなんです。ですから、いまイトウ保護のための行政的な予算措置というのはほとんどゼロです。それで、各生息地で活動している保護グループはとても苦労しているのですが、それでも少しずつ関係部局に働きかけて、公的な機関がこうした野生動物を、いわば国民の共有財産として保護管理していく方向性を、何とか作り出そうと努力しているところです。
さて、イトウの生態学について詳しいことは、後ろで販売させてもらっている「faura」誌(発行=ナチュラリー)をぜひご購読いただくことにして――手前味噌ですが、これほど懇切丁寧にイトウの現状を解説した雑誌記事というのは、これまでなかったと自負しています。まず何より、写真家の方たちの作品が素晴らしい。私は記事を担当したのですが、これはもう渾身の気持ちを込めています。イトウ特集は今年3月の発売号で、いま本屋さんには次の新しい号が並んでしまっているので、ぜひきょう、この機会にお買い求めください――
話を戻すと、国立環境研究所の福島路生さんが文献調査された結果によると、北海道ではこれまで42の水系でイトウの記録が残っているのですが、21世紀現在、個体群が確認されているのはわずか11水系です(福島路生「イトウ:巨大淡水魚をいかに守るか」/日本魚類学界『魚類学雑誌』55-1、2008年)。この急激な縮小は昭和時代に起きていて、ちょうど人間社会の高度成長期に当たります。流域の人口が増え、森林や草原や湿原が農地に変わり、水の利用量と排出量が増えて、川の姿がすっかり変わってしまうと同時に、川のイトウたちが「幻の魚」になってしまったのです。
巨体を誇るイトウは、水域生態系の中で、ちょうどサバンナにおけるライオンのような地位にあります。上流域から河口まで広大な水系全体を利用する生活スタイルを持ち、最高レベルの生物多様性なしに生き続けられない、そんな生きものなんです。逆に言うと、だからこそ、環境破壊の影響を真っ先に受けてしまったのでしょう。
こうした環境破壊は、決して過去のものではありません。この写真は、北海道東部、厚岸町の別寒辺牛川というイトウ生息地で、イトウの繁殖地を直撃する形で建設された砂防ダムです。2003年の冬に造られました。
イトウは春先、融雪増水が治まった直後ぐらいのタイミングで川を遡上し始め、本流域から支流・枝流の渓流のような環境に移動して繁殖行動を取る習性があります。その途中にこうしたダムが出来てしまうと、もう繁殖地にはたどりつけません。繁殖環境を守り、自然再生産のサイクルを壊さないことが、群れの健康を維持するための最低条件なのですが、ダムは最大の脅威なんです。
当時、このことが報道されると、さすがに道民の間から強い反感の声が上がりました。ダムを造った防衛省――ここ、自衛隊の演習場の中だったんです――は、対応を相談する第三者委員会を設けて、3年後、ダムを真っ二つに切断しました。それがこの写真です。元の環境とはほど遠い状態ではありますが、さいわい、間もなくこの上流でイトウの繁殖が再開しました。
新しいダムを切断するなんて、昔だったら考えられなかったことです。その意味では、21世紀は20世紀ほどひどい時代ではなくなってきているのかも知れません。たとえば今日の集まりはEarth dayにちなんだものですが、アメリカの一地方でこれが提唱され出したのは1970年、「アースデイEZO」のスタートが2007年。みなさんの環境意識の高まりが、国家政府を――何せ国軍ですよ――動かすまでになったと言えるかも知れません。
別寒辺牛川のダム問題を調べたい方は、イトウ保護連絡協議会のサイトをどうぞ。
さて、この地図は、いまかろうじてイトウ個体群が生きのびている場所を示しています。絶滅危機種にランキングされているとはいえ、各地の群れの健康状態はさまざまです。これはイトウに限らず、どんな野生動物に対しても言えることですが、人間が彼らにアプローチするときには、相手の様子をできるだけ慎重に見極めてから取りかからないと失敗します。
プレモニタリングといいますが、まずその群れの現状を把握し、具体的な対応を工夫して、実際に何か働きかけた後、またモニタリングをして、相手の状態がどう変化したかを確かめます。うまくいっていたら続けますし、状況が改善していなかったり、かえって悪化しているようなら、やり方を変えなくてはなりません。そうやって手探りで進めて初めて、野生動物の保護管理は前進するんです。
イトウ研究者のみなさんの研究成果によれば、たとえば猿払川水系・朱鞠内湖・金山湖、それに別寒辺牛川といった場所では、群れは世代交代がうまくいって、比較的健康な状態で暮らしています。こうした生息地では、環境を今のまま維持できさえすれば、当面はイトウたちの絶滅を心配する必要はありません。
逆に、十勝川・釧路川・斜里川といった場所では、イトウの生息は確認されているものの、繁殖に適した環境がほとんど失われているので、このままでは少子高齢化が急激に進んで、いずれ絶滅は免れない、と判断できます。
私たち「オビラメの会」がフィールドにしている尻別川は、残念ながら後者です。
尻別川は、ここから南区の定山渓を過ぎて、中山峠を越えたあたりから流れ始める大きな川です。幹流延長126km、流域面積は1640平方km、支流の数は283本を数え、喜茂別町、京極町、真狩村、倶知安町、ニセコ町、蘭越町と流れ下って、日本海に注いでいます。この尻別川が、現在、野生のイトウが生息する南限の川だとされているわけですが、猿払川などと違って、釣りを続けながらでもキャッチ&リリースすればイトウを守れる、というような楽観的な状況にはありません。
これは今から34年前、昭和51年(1976年)に撮影された写真です。若かりし日の草島清作さん、イトウ釣り名人といわれ、いま「オビラメの会」の会長をされていますが、こんな超大型が次々に釣れるほど、当時の尻別川は豊かな川でした。
「イトウ釣りのメッカ」とまで呼ばれたそんな尻別川で、急にイトウが釣れなくなってしまったので、危機感を持った釣り師たちが結成したのが「オビラメの会」です。1996年に発足しましたが、はじめの何年かかけて、イトウがどこで繁殖しているのか、さきほどの川村さんが中心になって、流域を徹底的に探してもらったんです。ところが全然見つかりません。結論は「この川にはイトウ繁殖環境がもはや残されていない。個体群としては絶滅したも同然」という厳しいものでした。「いま残っている生息地を保全する」というだけでは、もはや手遅れの状態だったのです。
かといって、放置しておけば本当に絶滅してしまいます。そこでやむをえず、人工孵化放流という「必要悪」を選択するほかありませんでした。
イトウに限らず、魚の人工放流は在来生態系に非常に高いリスクをもたらします。川魚たちの間に思わぬ病気を持ち込んだり、近縁種との間でDNAレベルの攪乱を招いたり、肉食魚や大型魚を放流すれば、既存の食物連鎖のバランスを壊しもするでしょう。いわゆる「外来種問題」を引き起こすのです。また、放流した魚自身にとっても、そのあとちゃんと健康に暮らしているかどうか。放流後にそれを見極める仕事も、簡単ではありません。
「オビラメの会」は2001年、「オビラメ復活30年計画」を立てました。これから30年かけて尻別川のイトウ個体群を復元し、最後には「イトウの釣れる尻別川」を取り戻して「オビラメの会」を解散しよう、という基本プランです。そこでは放流を重要なツールの1つと位置づけています。高いリスクを自覚し、常にそれを最小化しながら慎重に進めるといった条件を自らに課して、この手法全体を「再導入」と呼んでいます。
再導入を進めるにあたって参照しているのが、国際自然保護連合(IUCN)の再導入ガイドラインです。事前準備から事後に必要な諸作業、安定的な資金調達や合意形成まで、あらゆる課題のクリアを求める厳しいチェックリストですが、この中に候補地選定の大切さを述べた項があります。
「オビラメの会」の再導入計画の目標は、すっかり消えてしまったイトウ繁殖地の再創出です。川村さんたちの研究によれば、イトウは支流レベルの強い母川回帰性(生まれた川に里帰りして産卵する習性)があります。イトウの繁殖に適した環境を見つけて、そこへ稚魚のうちにイトウを放てば、いずれ4~6年後、親魚になって戻ってきて、繁殖行動に臨んでくれるかも知れません。自然繁殖がそうやって復活し、そうして生まれた子どもたちがまた親になって、いずれ放流なしで世代交代がうまくいくようになれば、再導入は成功です。
そのためには、絶滅要因の排除は欠かせません。尻別川でイトウの繁殖がうまくいっていない理由の1つは、やはりダムです。じつは、2004年に始めた再導入(放流)実験地=倶登山川でも、イトウ稚魚の成育に適した環境ではあるものの、本流までの間にいくつも小ダムがあって、自由な行き来が妨げられていました。
かといって、イトウのためにと勝手にダムを壊したりしたら、これは環境テロリストになってしまいます。ここはじっくり正攻法でいくしかありません。地元の倶知安町役場・北海道後志支庁・北海道小樽土木現業所真狩出張所にあてて「倶登山川におけるオビラメの遡上・降下を阻害する堰堤工の落差解消」を文書で要望するなどしたところ、幸い、後志支庁(現総合振興局)が魚道事業を計画してくれました。7年たった今年、全5基の農業用落差工のうち4基までに魚道が完成し、2010年度中に最後の落差工にも魚道がつくことになったのです。
オビラメの会は1998年から、尻別川で生け捕りにした――名人たちのグループとはいえ、たいへんな苦労がありました――イトウ親魚たちを飼育して、人工繁殖に取り組んでいます。これまた苦労の末に2003年に初めて人工孵化に成功し、そうして生まれてきた尻別川個体群の遺伝子を引き継ぐイトウの子どもたちを、これまで都合4回にわたって、さきほどの実験河川に放流しています。
もちろんガイドラインのプロトコルに従い、放流魚の追跡調査を続けて、放流イトウたちが無事に成長していることを確認しています。この地道なモニタリングは、生態学研究者の大光明宏武さんがリーダーを務めてくれていますが、みなさん、もし尻別川や倶登山川で釣りをして、若いイトウ――今では50センチほどに成長しています――を釣り上げたら、ぜひ「オビラメの会」に知らせてください。放流前にヒレの一部を切り取って目印代わりにしているので、一目で分かるはずです。そうした情報の積み重ねが、この再導入の試みがうまくいっているかどうかを判断する際の貴重なデータになります。
さて今日、この会場の議論のテーマは「川と魚をとりまく未来」です。「オビラメの会」の10数年にわたる取り組みを通して感じるのは、確かに困難な状況ではあるけれども、未来は決して暗闇ではない、ということです。
生きもの同士が作り上げる持続可能なネットワークのことを「生態系」と呼ぶとすれば、そのネットワークに再び、人間がじょうずにログインしていく工夫が求められていると思います。その時、社会が一体的になっていないと、なかなか持続するのが難しいでしょう。いち市民グループだけががんばる、というのではなく、地域の一般の住民や行政機関、さらに企業、よりひろい道民などが同じ思いを寄せて初めて、前進できると思うのです。そのためにはいろいろなセクターによる「協働」が欠かせませんし、情報を公開して世論に訴えることも大事。科学をツールとして使いこなせたら、説得力ある活動が実現できるでしょう。
いま「オビラメの会」は、放流したイトウたちが再び放流河川に戻ってきて、新しい魚道を通って繁殖地を見つけ、自力で産卵する姿を心待ちにしているところです。その時にはぜひみなさんにも喜びを分かち合っていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
アースデイEZOレクチャー&交流会(2010年6月27日午前10時、札幌市立札幌大通高校)での講演予稿。
無断利用を禁じます。
2010 (C) Hirata Tsuyoshi. All rights reserved.
